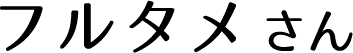
明治生まれの小さな体からは想像もつかないような大きな事業を成し遂げた実業家・爲三郎。若干18歳で養父の貴金属店を再興、商売を軌道に乗せると東京・大阪へ進出し、28歳には九州の炭鉱会社を買収します。まさに破竹の勢いで事業を切り拓き、経済恐慌下すらも、いち早く時代に左右されにくい現金事業へと舵をとり、31歳で名古屋大須に映画館「太陽館」を開館、映画事業へ進出します。その数年後には飲食業にも参入しました。更にこの非凡の実業家は、この時すでに不動産や株への投資へ注目し、着実に事業を拡大していきました。
しかし第二次世界大戦によって、これまで築いた全てが戦塵と消えるのです。それでも爲三郎の獅子の如き力は常識を覆し、翌年には映画館再興を果たします。同時に飲食と娯楽を兼ね備えた画期的なレジャー施設を誰よりも先駆けて手掛け、常に時代を先取りしていくのでした。
その後はリゾート開発、放送通信業界への進出も果たし、実に爲三郎が手掛けた事業は、映画産業から食品・食堂、温泉旅館、レジャー関係、不動産関係、山林事業と多岐にわたっています。一代で "古川帝国" たるに相応しい事業を成功させた希代の実業家・「古川爲三郎」の名は日本のみならず世界に轟くこととなり、98歳で海外の経済専門誌『フォーチュン』に世界最高齢の富豪として紹介され、その名を不動のものとしたのでした。
爲三郎の実業家としての手腕の秘訣は "時代を先読みする卓越した勘" "理不尽な力に負けない強靱な精神力" そして、何よりも "世のため人のため" にお金を惜しまなかったことでした。すべては人を喜ばせたいという一心から。無一文から自らの人生を切り拓いた爲三郎は、時代に愛され、自身も時代を愛し、そして人を愛した真心の実業家だったといえるでしょう。
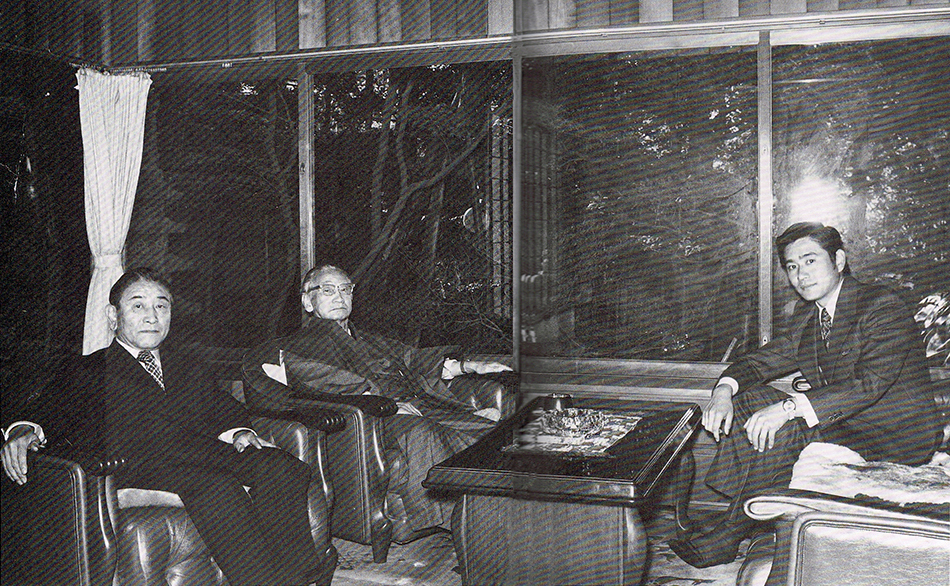
《生涯現役を貫く。だから生前に勲章は貰わない》と語っていた爲三郎。事業によって得た資産を教育や福祉に惜しみなく捧げました。
教育への支援
一代で多岐にわたる事業を興した爲三郎は、戦争や社会不安などで十分な教育を受けることができませんでした。多くは試行錯誤を重ねて独自に学んできたことを礎としたために、人知れぬ苦労もしていたのです。それ故に教育の必要性を人一倍感じており、未来ある若者、意欲ある者のためには協力を惜しみませんでした。
- ☆旧・古川図書館【現・古川記念館 名古屋大学博物館】
- 昭和39年 古川爲三郎・志ま夫妻の寄付により設立
- ☆古川サイエンス講演会(名古屋市科学館)
- 昭和40年、名古屋市市制100周年記念に対して行った寄付により、
- 平成元年以降、毎年開催されています。
- ☆豊かな教育を目指して、爲三郎の住居に近い地元小学校に、
- 長年にわたって楽器などの教材を寄贈。
社会福祉・医療への貢献
戦争や恐慌を体験し、激動の時代を生きた爲三郎は、安心して暮らせる地域社会、そして誰もが医療を受けられる社会の必要性を、誰よりも望んでいました。そうした志を実現すべく、社会福祉、日赤など医療への支援を行っています。特に昭和60年から晩年までは社団法人愛知県共同募金会「赤い羽根募金」の会長を務め、百歳になっても襷をかけて街頭募金に参加していました。また地域の発展のためにと世界デザイン博覧会や岐阜未来博等に多額の協力を積極的に行いました。
己の知恵と力で時代を切り拓いてきた爲三郎は、人一倍、信仰心の篤い人でした。そのきっかけは3回の命拾いにあります。1回目は九州の炭鉱会社の経営権を巡ったやくざとの争いで。2回目は、急性肺炎に罹り、棺桶に入ってから奇跡的に息を吹き返したこと。3回目は鉄道事故にあっても無傷だったことです。
そうしたことから、爲三郎は、人知を超えた大きな力の存在に自分は生かされているとの思いを抱くようになったのです。その思いは特定の宗教にこだわることなく、両親の菩提寺や各地の寺社への協力、世界33ヵ国へ平和を願う観音像の寄進、という形で表されました。
また爲三郎の感謝の心は大いなる力を持つ自然へも向けられます。特に《山が大好き。樹木の下へいくと樹木の精気が、もろに身に浸みるのがわかる。だから、山を買っても大きい木は絶対に伐らせない》との信念を持っていました。所有林にあった栃の巨木を「栃の木大明神」として大切にして祠をたてたほどです。現在は福井県大野市が所有しており、その栃の巨木は市の天然記念物として保護されています。
また、自らの住居としていた現・爲三郎記念館には5本の椎の巨木があります。余分な枝を払う以外は手をいれていない椎の木は、強い風や夏の容赦ない日射を遮る大切な役割を果たし、爲三郎の代わりに、記念館とこの地域一帯を今も見守っているようです。
実業家として卓越した手腕を発揮した爲三郎は、世界最高齢の実業家としても名が知られていましたが、半面「古爲さん」と、いつも笑顔の気さくなお爺ちゃんとしても親しまれていました。それは経営には厳格である一方で、従業員や地域の住民には限りない親しみを持ち、彼らのために何かできることはないか、とまるで孫を思うように大切にしてきたからです。爲三郎のその好々爺とした笑顔は、地域の人々の仕合わせあってこその、庶民の笑顔だったといえるでしょう。
地域社会の安全のために
愛知県少年補導委員会連合会副会長を務めていた爲三郎は、地域の防犯にも力を注いでいます。昭和17年の千種警防団団長の就任をはじめ、愛知県防犯協議会会長、名古屋市交通安全市民会議議長、家庭裁判所調停員、保護司会会長などを歴任しました。自らが理事長を務めた更正保護施設「更正保護法人立正園」では、青少年たちの社会復帰を願い、仕事の合間をぬってクリスマスや新年、節句などに夫人を伴って必ず訪れました。また、障害者自立支援施設「AJU自立の家」「ひかり学園」などへの協力も行っています。
実業家としてのイメージが強い爲三郎ですが、温かい心を持つ爲三郎の一面をうかがわせます。
地域の美術館建設の夢
若い頃から美しいものが好きで、美術品への造詣を深めてきた爲三郎。すぐれた美術品をはじめ、若手作家や地元作家の支援も積極的に行い、そのコレクションは実に2800点余となっていました。こうした美術品を多くの人々に楽しんでもらいたい、地域の人々に憩いの場を作りたいという爲三郎の思いは、やがて美術館建設の夢へと膨らんでいくのでした。
古川美術館の母体である『公益財団法人古川知足会』は、昭和62年9月5日に「財団法人古川会」として設立されました。平成元年3月には中区錦に「古川サロン&ギャラリー」を開設、爲三郎99歳を記念した「白寿展」にて夢の一歩を踏み出しました。そしてついに平成3年11月千種区池下町に長年の夢『古川美術館』が開館。「私蔵することなく広く皆様に楽しんでいただきたい」という想いが実現したのでした。現在は年数回の特別展と所蔵品を中心にした企画展を行うとともに美術講演会などの活動もしています。
古川美術館のコレクション

茶室のある純日本家屋を住まいとした初代館長古川爲三郎は、絵画や工芸品を鑑賞したり抹茶をたしなむなど、毎日の生活の中で芸術を楽しみました。戦前より美術品の収集を始めた爲三郎のコレクションは、いつしか膨大な数となり、その寄付をもとにした古川美術館の所蔵品は約2,800点にのぼります。親しみやすい美人画、花鳥画などの近代日本画を中心として油彩画、陶磁器、工芸品、また西洋中世の彩飾写本など、多岐にわたっています。
ハイビジョン
2階AVルームでは、古川美術館が制作した所蔵品解説の番組をハイビジョンで上映。作品が持つ微妙な色合いまで再現した映像を90インチの大画面でお楽しみいただいています。
遺志を引き継いで
明治・大正・昭和・平成を、獅子の如く鮮やかに駆け抜けた爲三郎の心を支えていたのは、人を喜ばせたいという思いと夢でした。一代で財を成し、その財を公共や文化の発展のために惜しみなく捧げることを望んだ初代館長・古川爲三郎の遺志を継ぐ公益財団法人古川知足会。来館する皆様への "おもてなしの心" が受け継がれています。
主な収蔵作家
| (五十音順) | ||
| 【 日本画 】 | ||
| 伊藤小坡 | ITO Shoha | |
| 伊東深水 | ITO Shinsui | |
| 上村松園 | UEMURA Shoen | |
| 上村松篁 | UEMURA Shoko | |
| 奥田元宋 | OKUDA Genso | |
| 小倉遊亀 | OGURA Yuki | |
| 片岡球子 | KATAOKA Tamako | |
| 鏑木清方 | KABURAKI Kiyokata | |
| 河合玉堂 | KAWAI Gyokudo | |
| 竹内栖鳳 | TAKEUCHI Seiho | |
| 寺島紫明 | TERASHIMA Shimei | |
| 徳岡神泉 | TOKUOKA Shinsen | |
| 橋本関雪 | HASHIMOTO Kansetsu | |
| 東山魁夷 | HIGASHIYAMA Kaii | |
| 平松礼二 | HIRAMATSU Reiji | |
| 福田平八郎 | FUKUDA Heihachiro | |
| 前田青邨 | MAEDA Seiton | |
| 森田曠平 | MORITA Kohei | |
| 安田靫彦 | YASUDA Yukihiko | |
| 横山大観 | YOKOYAMA Taikan | |
| 【 洋画 】 | ||
| 牛島憲之 | USHIJIMA Noriyuki | |
| 小磯良平 | KOISO Ryohei | |
| 杉本健吉 | SUGIMOTO Kenkichi | |
| 中川一政 | NAKAGAWA Kazumasa | |
| 森芳雄 | MORI Yoshio | |
| 脇田和 | WAKITA Kazu | |
| 【 名古屋市千種区ゆかりの作家 】 | ||
| 市野龍起 | ICHINO Tatsuoki | |
| 市野亨 | ICHINO Toru | |
| 鬼頭鍋三郎 | KITO Nabesaburo | |
| 田村能里子 | TAMURA Noriko | |
| 松村公嗣 | MATSUMURA Koji | |
古川美術館分館『爲三郎記念館』は、103歳までここを終(つい)のすみかとし、またこの住まいを愛した爲三郎の「創建時の数寄の姿をとどめる邸宅を皆様の憩いの場に」という遺志により、平成7年から広く公開するようになりました。現在、展覧会などを開催するほか、爲三郎の長寿の秘訣であったお抹茶などを楽しめる空間としても利用されています。
昭和9年に創建された爲三郎記念館は、茶事を目的に建てられた数寄屋(すきや)建築の『爲春亭』(いしゅんてい)と 四季折々の美しさを見せる日本庭園、そして、その中にひっそりとたたずむ茶室『知足庵』(ちそくあん)から成り立っています。
四季折々の美しさを見せる日本庭園、そして、その中にひっそりとたたずむ茶室『知足庵』(ちそくあん)から成り立っています。
各部屋には終日、光が充分差し込むよう南西向きにすこしずつ斜めに配置されており、その美しさは雁が群れて飛ぶ姿に似ているため「雁行形」(がんこうけい)と呼ばれています。柱と貫が交差する高床式の外観は桂離宮の書院建築を彷彿とさせます。
- 茶の間(ちゃのま)
- 爲三郎が居間として使用していた「茶の間」。現在でも壁掛時計が時を刻み続けるこの部屋は、名古屋の文化振興に情熱を注いだ爲三郎が自ら記した書道作品などを設えています。
- ひさごの間
- 爲春亭で、最も格調の高い部屋である「ひさごの間」。
 その名は、襖に漆で型押しされた瓢箪(ひょうたん)の模様に由来します。床の間横にある琵琶床(びわどこ)、欄間に施された源氏香紋(げんじこうもん)の透かし彫りの他、円形下地窓や木瓜形(もっこうがた)の無双窓など、桂離宮の意匠を連想させる建具の数々からは日本建築の精髄が感じられます。
その名は、襖に漆で型押しされた瓢箪(ひょうたん)の模様に由来します。床の間横にある琵琶床(びわどこ)、欄間に施された源氏香紋(げんじこうもん)の透かし彫りの他、円形下地窓や木瓜形(もっこうがた)の無双窓など、桂離宮の意匠を連想させる建具の数々からは日本建築の精髄が感じられます。 - 太郎庵(たろうあん)
- 浮観の間横の階段を下りると現れる茶室「太郎庵」。
 江戸時代中期の茶人、高田太郎庵好みの造りで、踏込み地板(ぢいた)の台目床(だいめどこ)に栗の山ナグリの床柱を立てた現叟床(げんそうどこ)になっています。襖には日本画家山本眞希氏による太郎庵椿が描かれ、この部屋の名前なった高田太郎庵をしのばせます。冬には、雪見障子から垣間見ることができる寒椿が室内の意匠と重なりあいます。
江戸時代中期の茶人、高田太郎庵好みの造りで、踏込み地板(ぢいた)の台目床(だいめどこ)に栗の山ナグリの床柱を立てた現叟床(げんそうどこ)になっています。襖には日本画家山本眞希氏による太郎庵椿が描かれ、この部屋の名前なった高田太郎庵をしのばせます。冬には、雪見障子から垣間見ることができる寒椿が室内の意匠と重なりあいます。 - 浮観の間(うきみのま)

- 邸内における唯一の洋間。吉柳満氏によって改築された壁は、「桜の間」と同じデザインでありながら、材質を変えることでまた一味違う雰囲気を演出しています。
- 葵の間(あおいのま)
- 極端に壁を少なくし、外の光と景色を多く取り込んだ茶室「葵の間」。台形の床の間には、
 板床が重ねられており、右に墨跡窓(ぼくせきまど)、左には円形下地窓(えんけいしたじまど)が抜かれています。また、天井の折上げ部分は市松の網代になっており、細部まで行きわたる数寄の意匠がうかがえます。正客から窓越しに庭園を一望できる工夫は、おもてなしの心の現われと言えましょう。
板床が重ねられており、右に墨跡窓(ぼくせきまど)、左には円形下地窓(えんけいしたじまど)が抜かれています。また、天井の折上げ部分は市松の網代になっており、細部まで行きわたる数寄の意匠がうかがえます。正客から窓越しに庭園を一望できる工夫は、おもてなしの心の現われと言えましょう。 - 大桐の間(おおぎりのま)
 市松の無双窓を通して庭園を望む「大桐の間」からの眺めは爲春亭の中でも最も美しく忘れがたい景観です。座敷名の由来となっている桐模様の襖。その上には杉と桐の木目を生かしながら山の重なりと遠近を表現した連山薄肉彫欄間(れんざんうすにくほりらんま)が、山にかかる雲をイメージした障子の桟と響き合いながら、深遠な雰囲気を演出しています。平書院の欄間には涼しげな水玉模様の透かし彫りが施されています。
市松の無双窓を通して庭園を望む「大桐の間」からの眺めは爲春亭の中でも最も美しく忘れがたい景観です。座敷名の由来となっている桐模様の襖。その上には杉と桐の木目を生かしながら山の重なりと遠近を表現した連山薄肉彫欄間(れんざんうすにくほりらんま)が、山にかかる雲をイメージした障子の桟と響き合いながら、深遠な雰囲気を演出しています。平書院の欄間には涼しげな水玉模様の透かし彫りが施されています。- 桜の間(さくらのま)
 平成8年、建築家吉柳満氏により生まれ変わった桜の間。数寄の建築を現在によみがえらせたこの空間では、洋画家・田村能里子氏による「季の嵐」(天井画:平成8年制作、壁画:平成19年制作)が楽しめます。天井から舞い振る桜吹雪が壁をつたいこの部屋を覆います。桜吹雪と楽器を奏でる女性は躍動する生命を象徴し、中庭に面した丸窓からは刻々と表情を変える光の中で風に揺れる孟宗竹(もうそうちく)を垣間見ることができます。
平成8年、建築家吉柳満氏により生まれ変わった桜の間。数寄の建築を現在によみがえらせたこの空間では、洋画家・田村能里子氏による「季の嵐」(天井画:平成8年制作、壁画:平成19年制作)が楽しめます。天井から舞い振る桜吹雪が壁をつたいこの部屋を覆います。桜吹雪と楽器を奏でる女性は躍動する生命を象徴し、中庭に面した丸窓からは刻々と表情を変える光の中で風に揺れる孟宗竹(もうそうちく)を垣間見ることができます。- 間想の間(まそうのま)
- 建築家吉柳満(きりゅうみつる)氏により平成19年の春に完成したこの部屋は、縁がない正方形の琉球畳と簡素な床の間から成ります。この部屋を囲う紅色の土壁は、これまでの和室のイメージを一新するもので、昔ながらの数寄屋建築に新しい風を吹き込みます。
- 庭園(ていえん)

- 5本の椎の木に覆われた庭園。「木には精霊が宿る」と考えていた爲三郎は、邸宅の創建前よりあったこの大木を大変愛しておりました。木曽川の「寝覚めの床」をイメージした岩組を流れる川は、邸内の大桐の間の意匠と重なりあう作りとなっています。時には、白砂の広場に檜(ひのき)舞台が造られ野点(のだて)やコンサートなど様々な催しが行われます。
- 知足庵(ちそくあん)
- 「足ることから知る」という利休の教えからその名をとった知足庵。尾張ゆかりの織田有楽斎(おだうらくさい)が建てた国宝「如庵(じょあん)」(犬山市)に想いを得た茶室です。端正な構えからは「きれいさび」の趣が漂います。二乗半台目向切(にじょうはんだいめむこうぎり)。
 床脇に斜めに壁をつくり三角の鱗板(うろこいた)をはめた趣向は如庵を踏襲していますが、台形の床や、亭主が下地窓を通して掛軸を見られるところは知足庵ならではと言えましょう。
床脇に斜めに壁をつくり三角の鱗板(うろこいた)をはめた趣向は如庵を踏襲していますが、台形の床や、亭主が下地窓を通して掛軸を見られるところは知足庵ならではと言えましょう。